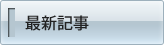次回作、『永久国債の研究』 発売日決定
先日からも申し上げていました『永久国債の研究』ですが、正式なタイトルと発売日が決まりましたので、本日はお知らせしたいと思います。
(このブログなどでも6月発売予定といってきましたが、予定より少し早まり、)
5月21日に光文社ペーパーバックスのシリーズとして発売されることになりました。
この本を出版する目的は、非常に実践的なものであって、永久国債発行による財源でもって日本経済を右肩上がりの方向に持っていこうということである。

この共著者の4人とも、その志では一致している。
この本が現実の政治を動かすようになってほしいと考えて、私も微力ながら、キャンペーンを展開していきたいと思っている。
この事は『ドンと来い!大恐慌』の第5章『日本が世界を救う』の章(167ページ)以下でも述べてきたが、この本では、170ページ以下で提案した「永久債」の、もしくは「超長期債」についてより詳しい理論を展開している。

この本は現実の財政再建とあるべき財政政策について議論しているが、本のかなりの部分が実は、非常に「概念思考(コンセプチュアル・シンキング)」によって構成されている。
財政政策というと数字について論じていると思われがちだが、この本に関しては全くそうではない。
この本は何よりも先ず、読者に、「国民にとって永久債とはどういうものか?」について説明しなければならない。
永久債とは、事実上、今まで存在してこなかったものであるから、我々は全く新しい国債の概念を創り上げ、それを国民皆に理解してもらわなければならない。
歴史上存在した、超長期債であるイギリスや薩摩藩の事例については事前に述べてある。
これらは250年償還の債券であったが、厳密に言えば永久債ではない。
つまり、今まで人間社会には恐らく永久債というものは存在しなかったはずである。
だから著者達は今まで全く存在しなかった概念を発明し、その概念を実現化しようと試みているわけである。
超長期債にしろ、永久債にしろ、最も大事なのはそれが、先ず人間の頭脳に「概念として存在」し、その後で、現実に存在しうるという事である。つまり、その存在自体が、非常に概念的かつ思考的なものなのである。
実は、我々が取り扱っている経済、特に金融とは極めて「概念思考」的なものである。
お金が存在するというのと、石ころが存在するというのでは、」存在という言葉の意味」が全く違っている。
石ころは何よりも先ず、人間の思考とは関係なく、物理的に存在している。
これに対して、お金や金融商品は先ず何よりも、人間の概念の世界に存在しているものである。
そもそも、「お金」というもの自体が今日においては極めて抽象的な概念である。
お金の本質は、決して目に見える「お札」ではなく、今日においてはコンピュータの中の数字に過ぎない。
つまり、人間の思考の生んだ抽象的な存在である。
これが、「お札」や「硬貨」に姿を変えることはあっても、その本質はあくまで抽象的な概念に過ぎないのである。
お金の本質が概念的なので、必然的に金融取引とは一般に概念操作そのものである。
企業が銀行から資金を借り入れ、これを返済する。
株式や債券といった様々な形の金融商品を創造し、これを取引する。
更には、細かな会計上の概念を導入し、企業や個人の資産を算定する。
これらはその、定義から取引に至るまでことごとく人間の「思考」の中の「概念操作」に過ぎないのである。
そもそも「借金」というものをどのように捉えるか?という事自体が実は、かなりの抽象的思考なのである。
そもそも借金に対して、利息が生じるという考え事態が「利子」という概念の発明に伴う概念思考である。
例えばイスラム世界では、「利子」という概念は存在せず、ただし「借金」に対する手数料というものが存在する。
違った例をあげれば、日本の中世では元金の2倍以上に元利合計がなる事はなかった。
つまり、借金に対する利子は、時間と共に永久に増え続けるわけではなく、時間的には利息が増えるのは480日までであった。
利子の総額としては、利子が元本と同じになるのが限界であった。
現在では、利息は時間と共に無限に増え続けるものであると我々は想定しているが、中世の日本人はそういう想定はしなかった。
つまり、借金に関する基本的概念が全く異なっていたのである。
企業に関してみると、株式と債権とは元来全くの別物である。
我々は厳密にこの2つを概念的に識別している。
株式は企業の所有権である。
債権は企業の借金である。
しかし、ここで、永久債権というものを考えてみるとその内容は無限に株式=所有権に近いものになってくるのである。
「永久国債」を概念上、どのように定義づけるかは意外に難しいことなのだが、その一番大事なポイントは借金が所有権に転化してゆくという概念操作なのである。
これだけの説明では分かりにくいと思うが、ともかくこの本をじっくりと読んで頂きたい。
そうする事によって、国の発行する永久国債を国民が持つとは、どういう意味なのか?というその意味が明らかになっていくだろう。
それはつまり、「官」でも「私」でもない「公」の領域の拡大なのである。
別の言い方をすれば、新しい国民共同体の構築に繋がる試みである。
CFG FAXニュース送信
今月は、やや早めにFAXニュースをレポート会員様に向けて送信した。
内容は主に、アメリカのストレス・テスト(大手金融機関の資産査定)の事についてである。
アメリカ政府によるストレス・テストの結果は甘すぎるのではないか?というのが私の正直な感想である。
ロシアのプーチン首相来日に関しては、領土問題での進展は殆ど期待できないが、日露間の原子力関係の協力については進展があるかもしれない。

休みの日だが、手紙を書いたり、夜は友人が訪ねてきてくれたりで、大変密度の濃い、充実した一日だった。
CFGのレポートについて、付け加えれば、今回のFAXニュースもそうだが、欧米のメディア・リテラシーという点に1つの焦点を置いている。
例えば、米FRBバーナンキ議長の発言に関しては表面上のことは伝えられている。
しかし、それをどう解釈するか?という点については日本のマスコミの解釈力は非常に弱いと言わなければならない。
バーナンキの発言をそのまま伝えるだけでは、謂わば情報の垂れ流しである。
彼が何を意図し、彼が何の為にそのような発言をしているか?を、分析し探求しなければならない。
そうでなければ、現実の真の姿は見えてこないであろう。
私のやっているのは、まさにその発言の解釈学である。
如何なる社会的文脈において、その発言がなされ、
バーナンキは如何なる意図をもってその発言をしたか?
そこまで深読みしなければ、分析が我々の行動の指針となる事はできない。
大げさに言えば、それがプロのインテリジェンスの作業である、という事になる。
多忙な経営者の方々、最前線のビジネス戦士にそういったインテリジェンスにかける多くの時間をそういったインテリジェンスの作業に割く事は極めて難しいの現実だ。
それで、謂わばその役割を代行するものとして、私の配信しているニュースサービスがあるわけである。
特に、国際情勢の潮目が大きく変わる時に、それを的確に予測する事はプロにも難しい作業である。
また、そこを的確に読まなければ、実務上、大きなチャンスを見逃したり、思わぬ損害を出したりする結果となる。
大企業ならば、こういったインテリジェンスの部門を会社の一部に抱えている訳だが、それでも、大企業の情報部門はとかく官僚主義化しており、変化してゆく国際政治経済の潮流に迅速に対応できない事が多い。
また、中小企業では、そういったインテリジェンスの部門事態を持つ事が殆ど不可能である。
そういった欠落した部分を補う為に一貫して、私は過去27年間、情報の発信の仕事に携わってきた。
情報発信は全て私個人の責任において行ってきた。
私に言わせていただければそこがきわめて重要で、権威や組織に頼ってのアリバイ作りを一切せず、全ての予測を最終的には自分の責任で行うという事が極めて大事であると思っている。
そして予測も現実に利用できるようにする為には、あいまいな形を出来るだけ避けて断言する形で行うようにしている。
必ず当たる予測の仕方というものがある。
それは三つの選択肢を掲げて、楽観論、悲観論、中間論の3つのシナリオを掲げてそのいずれかになると予測する事である。
しかしこれでは官僚の文章ではあっても、経営者が決断に生かすことに出来ない。
時に外れる事はあっても、自分の予測する「読み筋」をその理由を明快にして開示してゆくという事が本当のプロのあり方であると思っている。
誰々が言ったからこうであるとか、アメリカの某シンクタンクがこう言っているからこうであるというような外の権威に頼る予測もまた、意味がないものだと思う。
そういった覚悟で私はレポートを通じて情報発信を続けてきたつもりである。
(↑ ケンブリッジ・フォーキャスト・レポートについて)
山梨県の井尻先生宅にて、園遊会
本日は山梨県の塩山にある拓殖大学日本文化研究所所長、井尻千男先生の邸宅で毎年恒例の園遊会が開かれた。
井尻先生宅は、長屋門を構える3000坪の邸宅で、先生の一族は先祖代々この地の豪族・武士であり、この地に住み続けてきたそうである。
何しろ地名が、下井尻郡の井尻氏ということで如何に先生の一族の歴史が長かったか想像がつくというものであろう。

午前11時に先生宅に、日本文化研究所の関係者や、先生と交友のある方々が集い、昼食を共にしながら、大変楽しい座談のひと時を過ごした。
会のクライマックスは、『頌文邸(しょうぶんてい)』と、名づけられた茶室での濃茶の接待であった。
この『頌文邸』は先生、自らが設計された建物である。
言論人に人は多いといえども、自ら設計をして、茶室を建てる能力のある方は恐らく井尻先生ぐらいのものであろう。
先生のお話では、今後益々、形而上学的歴史論とでもよぶべき分野に力を傾注されたいとのことであった。
今後、益々、その方面において先生の天才的閃きが発揮される事であろう。
瑣末な事実や文献考証に捉われず、精神史としての歴史を追及するというのが恐らく形而上学的歴史論ということの意味であろう。
これはやはり、井尻先生ほどの学識と直観力をもってはじめて出来ることであると思う。
私が兼ねてから尊敬するのは、先生における一種の美意識と美的直観力の鋭敏さである。
そしてそれが、政治力や経済力と並んで歴史を形成する1つの力である事を見抜かれている、その鑑識眼である。
本日も秀吉と利休の関係などについて大変、斬新なお話を伺うことができた。
帰途は、チャンネル桜の水島社長や竹本忠雄筑波大学名誉教授と楽しく談笑しながら、東京に戻った。
『未来学の基礎と検証』シリーズ第1回 - 3 (/4) 藤井論文、20年前の論文を読む
 このブログ内での「連載シリーズ」として試みる事にした、『未来学の基礎と検証』シリーズ第1回の中の 『藤井論文、20年前の論文を読む 3 (/4)』、3回目として、本日は引き続き、「低開発国のディレンマ」をお届けしようと思う。
このブログ内での「連載シリーズ」として試みる事にした、『未来学の基礎と検証』シリーズ第1回の中の 『藤井論文、20年前の論文を読む 3 (/4)』、3回目として、本日は引き続き、「低開発国のディレンマ」をお届けしようと思う。
※ 1(/4) 「自由経済化の奔流」「なぜ共産主義は破綻したか」
2 (/4) 「裏切られた必然」
共産主義の脅威という場合、二つに分けて考える事ができる、というのが筆者の立場である。
まず第一に先進国においては、修正資本主義の考えは広まるにつれ、共産主義の脅威というのは非常に小さくなっていった。
これが前回の論点であった。
第二次大戦後の冷戦のプロセスにおいて実は共産主義の脅威とは主に貧しい低開発国において共産主義が拡まってゆくという脅威であった。
アメリカのタカ派を始めとする先進国の多くの人は、この低開発国に拡がる共産主義というものの中味を全く誤解していた。
世界の貧困地帯における共産主義の指導者は、共産主義イデオロギーによって洗脳されたインテリのグループではなく、祖国を貧困と搾取から救おうとする民族主義者であった。
王政や伝統的な貴族階級の存在しない社会においては、民族主義者は容易に左翼化し共産主義を受け入れるものである。
彼らが直面していたのは、16世紀以来の西洋の白人による凄まじい植民地主義による搾取であった。
低開発国は単に貧しいのではなく、先進国に搾取されているがゆえに、その経済構造を徹底的に破壊され、貧困に追いやられているのであった。
先進国では資本家=搾取階級、労働者=被搾取階級という図式は概ね非現実的なものとなった。
しかし世界の経済構造の中においては、先進国=搾取国家、低開発国=被搾取国家という図式はナンセンスなイデオロギーではなく、まさに現実そのものだったのである。
第三世界のリーダーにとっての現実とは、先進国の多国籍企業によって労働と自然資源は安く買い叩かれ、かつて存在した伝統的農村共同体は外国資本によって買い叩かれ、庶民は貧困の極致を彷徨うというようなものであった。
男の兄弟は、麻薬を売り、妹は売春をし、家庭は崩壊している。
そのような現実はあまりにありふれていた。
そのような現実を救おうとする時に、マルクス主義理論は確かに1つの力となった。
南北間の経済搾取構造を否定しなければ、低開発国は永久に自立を達成する事はできない。
南北問題とは、北=先進国、南=低開発国の間に存在する階級的搾取構造の問題である。
そのような経済構造を前提とする限り、低開発国の多くにとって、共産主義が自立の為の1つの選択肢であったのは事実であった。
先進国との交易関係を否定すれば、経済発展の元となる資本や技術を導入する事は極めて難しくなる。
それ故に、毛沢東やカストロやホー・チミンが目指したのは、豊かになる事ではなく、自立し、国を閉じ、貧困を平等に分かち合う事であった。
貧困ではあっても、そこには、民族の自立と国民の平等が有り得たのである。
以上のように理解する時、低開発国にとって、共産主義が何を意味していたのかが極めてよく理解できる。
低開発国の共産主義のリーダー達にとって、豊かさよりも自立のプライドこそ最も重要なものであった。
以上のような視点から、今回の連載第3回目の論文を読解して頂きたいと思う。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
※ 以下は、10ページの論文記事を4回に分けてお届けするシリーズの第3回分である。
(中央公論1989年9月号掲載論文 『共産主義「終焉」の後に 』 より)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【 4.低開発国のディレンマ 】
共産主義を第二次大戦後の国際政治において論ずる場合、低開発国への共産主義の拡大が重要なテーマになってきた。
ロシア革命時のロシア自体が、ヨーロッパの中ではきわめて工業化の遅れた後進国であった。
中国もまた圧倒的な農民・農業国であり、この農民の心を掴むことによって、毛沢東は中国革命に成功した。
経済先進国において共産主義のアピールが早くから激減した事実はすでに述べたが、第二次大戦後に共産化した国は、低開発国に共産主義が蔓延し、先進国が共産主義化した低開発国によって包囲されてしまうのではないか―という恐怖感が存在してきた。
一時喧伝されたドミノ理論とは、1つの低開発国に共産化を許せば、これがゲリラ戦略によって周囲の国に伝染病のように広がり、周辺の国が次から次へ共産化してゆく ―という西側先進国の、特にアメリカの憂慮をほとんど戯画的な形でモデル化したものである。
ではそもそも、低開発国にとって共産主義とは一体なんだったのだろうか。
外国からの援助を受けたかも知れないが、主に内発的理由から共産主義を採用した国々にとって、共産主義とはまず第一に、先進国の搾取なき経済であり、第二に民族の完全独立であり、第三に平等に貧困を分かち合う状態であった。
ソ連・中国をも含め、共産主義が現実に約束し、達成したことはこの三つであったと言える。
民族の自立・自治を先進国の帝国主義政策に抗して勝ち取ること。
そして名目的な政治的独立ばかりでなく、経済的にも新植民地的搾取状態から脱して、独自の経済建設を進めること。
これが、カストロが、ホー・チミンが、毛沢東が掲げた目標であった。
たとえ政治的・名目的に独立を勝ち得ても、現代の世界では南北間の経済構造のゆえに、先進国(北)は低開発国(南)に対して有利な形で交易を進め得る。
低開発国側は、農作物・自然資源等の一次産品を安価に提供するか、低賃金労働を先進国からの進出企業に売るしかない状況に追い込まれる。
こういった悲惨な状況から脱却しようとすれば、自ずと資本主義経済の国際的ネットワークから完全に離脱して自国の経済建設を考えてゆかざるを得ない。
かつては、政治的な完全独立さえ許されなかった。
やがて政治的には独立できても、経済的には従属構造に組み入れられることになった。
このような厳しい外部条件が存在したのである。
ここに、共産主義が1つの現実的選択肢として現れてきたのである。
ヨーロッパ滞在時代のホー・チミンは、社会民主主義系統の第二インターと、より過激な第三インターのどちらに参加しようかと迷ったが、第三インターを選んでいる。
当時のホー・チミンにとって第二インターと第三インターの間の路線上の相違は理解も出来ないし興味もなかった。
彼が第三インターを選んだ理由は唯1つ、第三インターの方がベトナムのフランスからの独立をより明確に支持していたからである。
カストロがキューバ革命を遂行中の時、彼は共産主義者だったわけではない。
カストロが目標にしていたのは、欧米、特にアメリカの植民地状況にある悲惨な祖国を救済し、そこに住む人々の暮らしを少しでもまともなものにすることであった。
そのために、彼はすべての合法的闘争手段の尽きた後、ゲリラ戦争という実力によって、腐敗の極致にあった、時のバチスタ政権を打倒したのである。
カストロは初めから反米であったわけでも、親ソ的共産主義者であったわけでもない。
キューバを反米・親ソの共産国に追いやったのは、主にアメリカの対応が誤まっていたためである。
アイゼンハワーからケネディーに替わった当時のアメリカは、キューバの国情に関する無知から、旧バチスタ政権の流れに属するような人々を支援し反革命を後押しした。
これがカストロの離反を決定的にし、キューバ・ミサイル危機は米ソ冷戦構造の中に、がっちりとキューバを組み込んでしまった。
しかしそのキューバも、ソ連共産主義経済が破綻し、構造的デタントの流れが決定的となる中で、西側への経済開放に徐々に動きつつある。
ベトナムも、外資導入・開放政策・自由化の方向に大きく方向転換してきた。
共産主義化した低開発国は確かに“平等に貧しい”状態には成り得た。
しかしそこから先に進む事はできなかった。
しかし、80年代から90年代への新しい世界の状況は、共産主義化しなくても、政治的に自立し、資本主義経済圏にとどまったまま経済近代化を可能にするような客観情勢を作り出しているのである。
それゆえに、すでに共産化した国々も自由経済化・開放政策に向かい、共産化していない国々にとっては、共産主義的近代化の道はおよそ魅力の無い、ナンセンスなものになってきたのである。
民族主義者にとって共産主義は所詮借り物であった。
今や共産主義という、お仕着せの貸衣装を脱ぐべき時が来たのである。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
※ 次回は、第4回連載の最終章、 【第5章、新たな世界経営に向けて】 に続く。
この企画の紹介論文は、4回に分けてご紹介させて頂きます。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【 第3回掲載分の 補足的解説 】
この論文を書いてから4年か5年程後だったと記憶しているが、キューバを訪れる機会があった。
残念ながらカストロ首相に会う事は出来なかったが、第一副首相には会う事ができた。
会見は少人数で一時間ほどであった。
私は前日、徹夜で書いたスペイン語のカストロ宛の手紙を持っていった。
第一副首相にその手紙を渡し、カストロに必ず直接手渡してくれと頼んだ。
彼は、快く引き受けてくれた。
カストロが私の手紙を読んでくれたかは分からない。
その後、何の返事も彼からはもらっていない。
しかし、私の手紙はそもそもカストロから答えが来るような類の手紙ではなかった。
私がその手紙で書いたのは、こういうことだ。
カストロは偉大な指導者であり、愛国者である事は確かである。
彼は、奴隷的な立場にあったキューバ国民を解放し、彼らに独立と自尊心を与えた。
カストロにとって共産主義はあくまで、自立を達成する為の方法であり、手段であったに過ぎない。
今、キューバ国民は誇り高く、自立した国民になった。
しかし、豊かになる事は出来ないでいる。
まして、ソ連邦が崩壊し、ソ連からの経済援助は無くなってしまった。
人々は、基本的な物資の欠乏に悩んでいる。
私はカストロに、今こそ、頑なな共産主義をやめ、市場経済を導入し、西側諸国とも大いに経済交流を始めるべきだと提案した。
政治的に完全な独立国家となった以上、以前のバチスタ政権下のような外国資本による搾取は最早不可能である。
共産主義は独立・自立の手段に過ぎなかったのだから、時代の変化に従って、その手段が無効になれば、それを投げ捨てて他のより有効な手段を採用すればよいではないか?
以上のような趣旨の手紙であった。
それ以降のキューバーの行き方を見ていると、ある程度の私有財産と市場経済の導入を行っており、私の手紙もまんざら無駄ではなかったのかもしれない、と思いたくなる。
又、ここでカストロとゲバラに関する非常に面白いエピソードを2つ紹介しておきたい。
カストロは昭和天皇が崩御された時、その死を悼み、キューバ国は一週間にわたって半旗を掲げた。
この一週間というのは諸外国の中でも異例の長さであった。
そしてカストロは、おそらく何年かぶりに日本大使館を訪れ、駐キューバ日本大使と深夜まで昭和天皇の死を追悼し、懇談したのである。
カストロが英米と闘った昭和天皇を如何に尊敬していたかが、この一事をもってしてもよく分かる。
日本の左翼がおろかなのは、このようなカストロの「心情」を全く理解できない事である。
要は、民族の独立と民生の充実こそが政治の真の目的なのであり、共産主義イデオロギーなどは、二次的三次的な手段に過ぎないのである。
革命の大臣となったゲバラが日本訪問をした。
この折、彼は約2週間にわたって日本に滞在し、主に各種の工場を見学して回った。
キューバの経済発展のためには、工業化がどうしても必要であり、その為には日本に大いに学ぶべきところがあると考えていたからである。
アメリカに敗戦したにもかかわらず、世界一流の工業力を発展させつつある日本にゲバラは大いなる感銘を受けたようであった。
このゲバラの「心情」も日本の左翼のおそらく全く理解できないところであろう。
最近、ゲバラの映画が日本で公開された。
ゲバラが直面していた現実とは、まさに論文の前の解説で述べたような南北問題の圧倒的な現実であった。
貧困と搾取は、本の中にではなく、現実の路上に溢れていた。
そのような視点からゲバラの映画も観なければならないと思う。
ゲバラ映画についての感想と批評はまた別の機会に譲りたい。
西部先生の「人生論」に酔う
今夜は西部先生と久々にお逢いでき、楽しく酒盃を重ねる事が出来ました。

『だからキミの悩みは黄金に輝く - 西部邁の人生相談』は本当にすばらしい本だと思う。
今の10代から20代の人が読めば、必ず多くを学ぶ事ができると思う。
というのは、多くの若者に共通した悩みを相談者が尋ねているからだ。
例えばそれが引きこもりであり、いじめであり、リストカットであり、失職してしまった派遣社員の問題であるからだ。
西部先生はそれらの質問者に同情しつつも、広い視点から彼らや彼女らや悩みを笑い飛ばすようにその回答を与えている。
そこには同情と超越とが同時に存在している。
心の中の遠近法が確実に担保されている。
そのような人生の達人からのとても具体的なアドバイスは現代の禅問答といってもいいと思う。
おそらく、相談者はその悩みを一刀両断されながらも、大いにその一刀両断の刃に愛情を感じてあるはずである。
その刃は、現実という殻や、一見破壊しがたい現状の壁を安々と鮮やかに破壊し、明日への希望をひらく刃である。
一瞬、川端康成の「雪国」の”国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。” という文章を思い出す。
トンネルを抜けた「夜の底が白くなった」世界を見たい君にお勧めの「刃」である。
しかし回答者は「希望には常に自己責任が伴う」という人生の約束を再確認している。
56歳の私が読んでも、実に面白くためになる現代の禅問答である。
この一切の答えが全て即興で即時にその回答が与えられているということはまことに驚嘆すべき事ではないか?
回答者は書斎に篭って回答を熟慮して与えるのではなく、口頭によって即断即決でその回答を鮮やかに与えている。
これを人生の超達人といわずして何といおう?
読めば分かる!といいたい本である。

詳しくは、ジョルダンブックス『読書の時間』の『西部邁の人生相談』のページ
http://book.jorudan.co.jp/cgi-bin/browse.cgi?action=1&file=jinsei
を見て欲しい。
- 2016年09月
- 2016年07月
- 2016年06月
- 2016年05月
- 2016年04月
- 2016年03月
- 2016年01月
- 2015年12月
- 2015年10月
- 2015年09月
- 2015年07月
- 2015年06月
- 2015年02月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年09月
- 2014年06月
- 2014年05月
- 2014年04月
- 2014年03月
- 2014年02月
- 2014年01月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年09月
- 2013年08月
- 2013年07月
- 2013年06月
- 2013年05月
- 2013年04月
- 2013年03月
- 2013年02月
- 2013年01月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年09月
- 2012年08月
- 2012年07月
- 2012年06月
- 2012年05月
- 2012年04月
- 2012年03月
- 2012年02月
- 2012年01月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年09月
- 2011年08月
- 2011年07月
- 2011年06月
- 2011年05月
- 2011年04月
- 2011年03月
- 2011年02月
- 2011年01月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年09月
- 2010年08月
- 2010年07月
- 2010年06月
- 2010年05月
- 2010年04月
- 2010年03月
- 2010年02月
- 2010年01月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年09月
- 2009年08月
- 2009年07月
- 2009年06月
- 2009年05月
- 2009年04月
- 2009年03月
- 2009年02月
- 国際情勢(海外のニュースなど)(401)
- 未来学(94)
- 国内情勢(349)
- 近況ニュース(活動記録など)(417)
- Media Review(148)
- エッセイ(40)
- 詩・俳句(39)
- 芸術活動(芸術関係)(18)
- 「ドンと来い!大恐慌」関連(33)
- その他(10)
- 311・原発事故関連(9)
- NHK捏造事件と無制限戦争(72)
- 「永久国債の研究」関連(10)
- 「鳩撃ち猟」レポート(8)
- 【藤井厳喜アカデミー第1弾・国民の為の政治学シリーズ】(18)
- 【藤井厳喜アカデミー第2弾・日本を復活させる智恵─増税を許すな!】(4)
- 【藤井厳喜アカデミー第3弾・国際関係論入門】(8)
- 政治学(21)
- 特集『東アジア共同体は亡国への道』大シナ帝国成立を阻止せよ(8)
- 猫・Animal関係(10)
- FMラジオつくば【KENNY'sProject】(84.2mhz/TUE/22-23)(34)
- シリーズ 『共和制革命を狙う人々』(9)
- 藤井厳喜の最新刊『あなたも国際政治を予測できる! 最強兵器としての地政学』9月16日、ハート出版より発売開始
- 藤井厳喜の最新刊『「国家」の逆襲 グローバリズム終焉に向かう世界』8月1日、祥伝社新書より発売開始
- 「欠陥ヘイト法と日本の危機」を中山成彬候補と語る国民集会でスピーチ
- 藤井厳喜『英国EU離脱大歓迎論:国家を取り戻すNeo-Nationalism』AJER2016.6.30
- 倉山満さんの番組【チャンネルくらら】に出演【6月28日配信】特別番組「近衛上奏文を語る」国際政治学者藤井厳喜
- 藤井厳喜『<特番>西村眞悟先生大いに語る』AJER2016.6.21
- 【チャンネルくらら】に出演:【6月4日配信】倉山満が訊く、国際政治学者藤井厳喜さん「パナマ文書タックスヘイブン問題なぜ今出てきた?これからどうなる?」
- 【日本ウイグル連盟主催シンポジウムin Tokyo前篇】アジアの「孤児」?ウイグル政治亡命者の現状と日本の役割
- 第12回 加瀬英明×堤堯「つつみかくさず」?我々が本気で話す日本の裏舞台? ゲスト:藤井厳喜「アメリカのデタラメ外交」 Part2
- パナマ文書公開日に「ザ・ボイス!そこまで言うか!」出演